社会保険労務士
働き方研究所 MiRAHATA
働き方改革

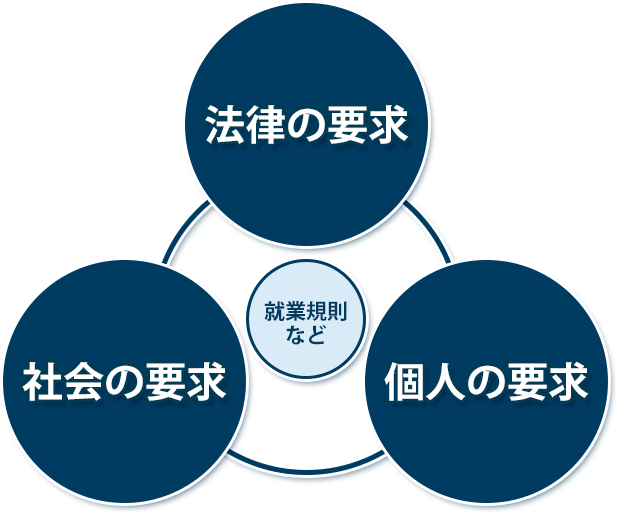
社会保険労務士
働き方研究所 MiRAHATA
働き方改革

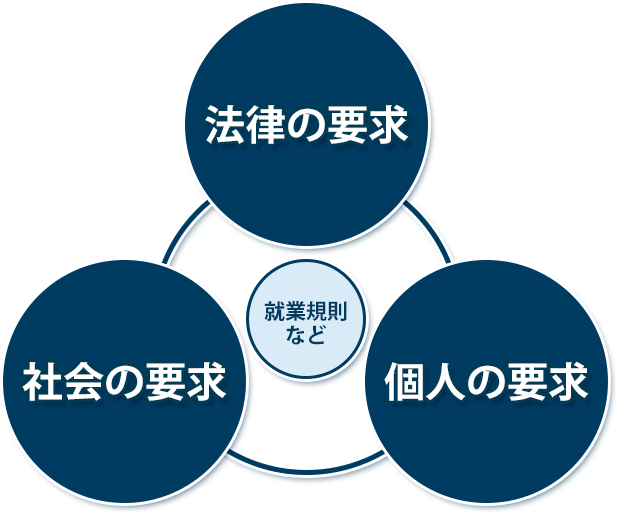

働き方改革については、
2016年9月に「働き方改革実現会議」が設置され、2017年3月には「長時間労働の是正」「柔軟な働き方がしやすい環境整備」など9分野における具体的な方向性を示した「働き方改革実行計画」がまとめられました。
そして、2018年6月には「働き方改革法案」が成立、2019年4月から「働き方改革関連法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)」が順次施行されています。
「働き方改革関連法」とは、以前より制定されていた。
に、上記の方向性に沿った改訂を加えたもので、
主要な内容として、
があり、長年にわたって、「働き過ぎ」と揶揄されてきた、日本の「働き方」に大きなメスが入れられることとなったのです。
とはいうものの、長期間にわたって慣習として続いてきた「働き方」を改革していくのは、労使双方にとって、戸惑いも多分にあっただろうと推測します。
特に、従来青天井であった超勤についても、
数値的な規制ができたこと、そして、その上限を超えずとも、残業そのものに対する社会の見方も随分変化してきたこともあり、使用者側にとっては、その削減については、大きな痛みもあったことでしょう。
一方、労働者側についても、仕事内容が変わらないまま、時短を強制的に求められ、ある意味、労働強化や、隠れ残業などの問題が出てきたり、早く帰ることで、家庭からうとましく思われたり、それがいやで、途中で寄り道をしたり(フラリーマンと命名されましたね。)
と、ペースを乱されたことも多いでしょう。
しかしながら、長時間労働の削減というのは、健康の保持や人間的な生活のため、あるべき姿であって、すこしは「いやいや働く社員」の削減に貢献した面はあるかもしれません。
ただし、長時間労働が一元的に悪というわけではなく、時期と内容によれば、望ましい姿である場合があるということも否定はできません。
ここでもやはり、「いやいや働く」のではなく、「活き活き働く」「主体的に働く」のであれば、それは賞賛されるべきシーンもあることでしょう。
そして、2021年6月に、
「経済財政運営と改⾰の基本⽅針2021 〜⽇本の未来を拓く4つの原動⼒〜(令和3年6月18日)」
が閣議決定され、
労働時間削減などを行ってきた「働き方改革フェーズI」に続き、
メンバーシップ型からジョブ型への雇用形態の転換を図り、
従業員のやりがいを高めていくことを目指す「働き方改革フェーズII」の推進が図られようとしています。

これが、まさに当事務所が取り組んでいる「活き方改革」になるのでしょうが、
これは運用や理解を一歩間違えれば、また各企業はあさっての方向へ進みかねず、慎重な取り組みが必要となってきます。
フェーズIIの働き方改革の内容は、
などとなっており、まさに迷走しかねない話題ばかりです。
ぜひとも、よく理解し、考え、最適、最善で生産性向上、「活き方改革」につながる、いい改革を行っていきましょう。
働き方研究所MiRAHATAでは、
「会社、従業員がWIN-WINとなる働き方」の
研究と創造、実施の
ご提案、お手伝いをさせていただいております。
フェーズⅠ
事前打ち合わせ
改革の方向性、取り組み方針の説明、確認
▼
現状把握
各人の就業実態の確認(1W)
▼
課題、問題点の抽出
それぞれの改革への問題点整理(1W)

フェーズⅡ
あるべき姿の確認
あるべき姿と現実のギャップを認識(1W)
▼
対応可能事項の洗い出し
対応可能事項を特定(1W)
▼
対応方針の策定
対応の方向性を確定(1W~2W)

フェーズⅢ
対応取り組みの実施
対応実施(1W~6M)
(大きな場合は外部委託などを含む)

フェーズⅣ
効果の検証
取り組み実施後、効果を数値化して検証(1W)
▼
評価
最終評価
▼
積み残し事項の確認
将来の課題を確認

フェーズⅤ
将来計画
今後の対応計画を策定する
標準取組期間:6か月
《関連ページ》

Copyright © 2025 働き方研究所 MiRAHATA All Rights Reserved.
大阪府大阪市北区万歳町3-12 TEL 090-1967-2223
powered by Quick Homepage Maker 7.6.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK